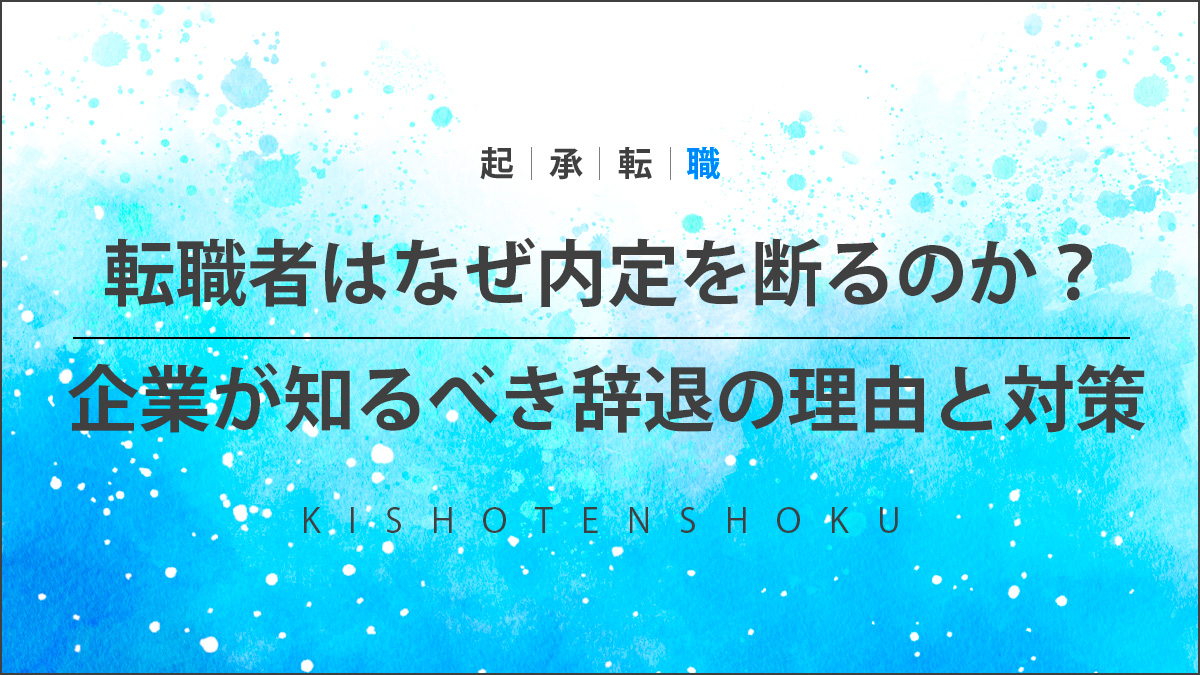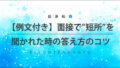採用活動には多くの時間とコストがかかります。しかし、どれだけ入念に進めても「内定辞退者」が出てしまうと、費用や時間が無駄になってしまうだけでなく、確保したはずの人材が離れてしまうリスクも伴います。
企業にとっては避けたい事態ですが、一方で求職者からすれば「辞退」は選択肢の一つ。法的にも雇用開始の2週間前までは辞退が可能とされており、納得できる企業選びのために内定辞退を選ぶことは合法です。
本記事では、内定辞退が起こる理由や、企業が実施すべき対策を解説。求職者の皆さんは企業選びの参考に、採用担当の方は採用戦略の改善にぜひ活かしてみてください。
なぜ内定辞退は起こるのか?
せっかく時間と労力をかけて内定を出したのに、候補者から辞退の連絡が入ると、採用担当者としては「どうして?」と疑問に思ってしまうものです。ですが、内定辞退の背景には、単なる気まぐれではなく、求職者側の事情や企業との相性、そして転職市場のリアルが大きく影響しています。
求職者の選択肢は豊富
今の転職市場は売り手優位とも言える状況で、特に経験やスキルがある人材ほど、複数企業から内定を獲得するのは当たり前になってきています。ITや営業などの専門職はもちろん、職種を問わず「良い人材をなんとしてでも採りたい」と企業側が積極的に動いているため、求職者にとっては選択肢が非常に広がっている状態です。
その結果、「内定が出た=すぐ入社」という流れにはならず、「複数の内定の中から、最も自分に合った企業を慎重に選ぶ」というフェーズが発生します。この段階で、職務内容、働き方、福利厚生、社風など細かく比較検討したうえで、最終的に辞退という選択に至る場合も多いのです。
また、転職活動は現職と並行して進められることが多く、「本当に転職すべきか」「今の職場に残った方がいいのでは」といった迷いや葛藤の中で、状況が変化すれば内定辞退の判断に切り替えることも十分あり得ます。
さらに、法的な観点でも求職者には辞退の自由があります。民法第627条によって、雇用開始の2週間前であれば退職(辞退)を申し出ることが認められており、内定承諾書に法的な拘束力はありません。つまり、求職者は最終的に自分にとって最良の選択をする権利を持っており、内定辞退は冷静で合理的な判断とも言えるのです。
求職者が企業に「NO」を出す理由とは?
「内定をもらったらすぐに入社するはず」と思っていても、実際には求職者が内定を辞退する理由はさまざまです。企業がいくら魅力的なオファーを出したとしても、それだけで「入社する」とは限りません。求職者は、自身のキャリア、価値観、生活環境などを総合的に考慮したうえで、最終的な判断を下しています。
ここでは、求職者がなぜ企業に「NO」という選択をするのか、実際に多く聞かれる内定辞退の背景とその要因について詳しく見ていきましょう。企業が気づきにくい視点や、採用活動を改善するヒントにもなるはずです。
給与・待遇への不満
給与や福利厚生は、多くの求職者にとって転職を決断する上で最も重要な判断材料のひとつです。面接や内定の段階で提示された条件が、スキルや経験と釣り合っていないと感じた場合、「この企業では正当に評価されていないのでは?」という不信感につながりやすくなります。特に優秀な人材ほど複数社からオファーを得ているため、他社との条件比較によって冷静に辞退を選ぶケースが多く見られます。
職務内容・役割とのギャップ
「想像していた仕事と違う」という違和感は、内定後の辞退につながりやすい要因です。求人票や面接での説明では魅力的に映った仕事も、実際の業務内容やポジションを詳しく聞いた途端、理想とのズレを感じてしまうことがあります。特に、キャリアチェンジや専門性を活かしたいと考えている人にとっては、「やりたいことができないかも」と感じた瞬間に、別の企業を選ぶ判断が加速します。
キャリア成長への期待が持てない
仕事を通じて自身のスキルを磨きたい、将来的にはリーダーシップを担いたいという成長志向の高い求職者ほど、会社の制度や文化に敏感です。「この企業では自分が成長できるイメージが持てない」と判断された場合、内定を受けるメリットが見い出せなくなり、辞退という選択肢に傾くのは当然とも言えます。
企業文化や柔軟性への懸念
面接や社内見学、社員との会話を通じて「社風が合わないかもしれない」「思ったより保守的な雰囲気だ」といった直感を抱くことがあります。また、フレックスタイム制度がない、リモート勤務が認められないなど、働き方の柔軟性に欠ける点も、現代の求職者にとっては大きなネックになります。「この職場では自分らしく働けないかも…」という不安が出てくると、内定辞退につながる可能性が高まります。
転職によるリスクが大きい
転職はチャンスであると同時に、大きなチャレンジでもあります。特に現職に不満がない、すでにポジションを確立している求職者ほど、転職による「失敗リスク」には敏感です。安定した今の環境を手放してでも行きたいと思えるほどの魅力が企業側から伝わってこない場合は、結果として現職残留を選ぶのも自然な流れです。
面接対応やコミュニケーションへの不満
採用プロセスの中での企業側の姿勢や対応も、内定辞退のトリガーになり得ます。連絡が遅い、質問への回答が曖昧、スケジュール調整がスムーズに進まない…といった経験があると、「この会社で働くのはストレスが多そうだ」と感じられてしまいます。企業の対応一つひとつが、候補者にとっての信頼感や安心感に直結していることを忘れてはいけません。
家庭事情やプライベートな要因
転職活動中には、求職者の私生活にもさまざまな変化が起こる可能性があります。子どもの進学、配偶者の転勤、親の介護など、家族に関する事情が絡んでくると、タイミングや勤務地に制約が生まれることもあります。こういった事情が理由で、当初前向きだった転職を見送るというケースも十分にあり得ます。
オファー条件が不明確
内定を出されたものの、細かい条件が曖昧だったり、説明不足だったりすると、求職者は将来への不安を感じます。給与体系、評価制度、昇進の条件などが不透明なままだと、「この会社で長く働けるイメージが持てない」と考えてしまい、他社の方が安心できると思えば辞退へと傾いてしまうでしょう。
勤務地・転勤の懸念
勤務地や転勤の条件は、ライフスタイルに直接影響を与える重要な要素です。自宅からの通勤が困難だったり、転勤の頻度が高い企業だったりすると、求職者にとって「生活とのバランスが取れない」と感じられることがあります。家族と一緒に過ごす時間や、子育てとの両立が難しくなる可能性がある場合は、内定を辞退して別の選択肢を探る流れになるのも自然です。
採用担当者にできる内定辞退対策
内定辞退は、どんな企業にも起こり得る課題ですが、単に運が悪かったという話では片づけられません。実は、企業側の対応次第で、求職者の不安や疑念を解消し、「この会社で働きたい」という気持ちを引き出すことは十分可能です。
採用担当者として、求職者が最終的に辞退という選択をする背景を理解し、それに対して適切にアプローチしていくことが求められます。ここでは、実際に現場でできる内定辞退を防ぐ対策を具体的に紹介します。
誠実でスピーディな対応を徹底する
採用活動の第一歩は、信頼関係の構築です。求職者にとって、面接や選考は企業との“初対面”とも言える重要な場面。その中で、企業側のレスポンスの遅さや対応の曖昧さを感じ取ってしまうと、「この会社は本当に自分を歓迎してくれているのか?」という疑念が芽生え、志望度が下がってしまう可能性があります。
たとえば面接日時の調整や合否連絡、質問への返答など、一つひとつのやりとりをスピーディかつ誠実に対応することで、求職者は安心感を覚え、「信頼できる会社だ」という印象を持ってくれます。また、選考中の疑問を気軽に相談できるよう、社内見学会や社員との座談会などの“聞きやすい空気づくり”も非常に効果的です。
面接時に正確な情報を提示する
求職者は、会社の提示する条件や環境をもとに、将来像を具体的に描こうとします。仕事内容や給与体系、労働時間、昇進の見込みなどが不明確だったり、説明に食い違いがあったりすると、「この会社に入っても安心して働けるだろうか」と不安が募ります。
そのため、面接の場では法令で定められている労働条件の明示はもちろん、会社としての強みや今後の展望、キャリアパスまで丁寧に伝えることが大切です。特に求職者が遠慮して質問しにくい待遇面は、企業側から積極的に説明し、理解を深めてもらう姿勢が求められます。誇張表現や曖昧な情報で期待だけを膨らませるのではなく、リアルな会社の姿をしっかり伝えることが信頼獲得につながります。
内定後も定期的にコンタクトを取る
面接を終え、内定を出した後も気を抜いてはいけません。入社までの期間に企業側から何の連絡もなければ、求職者は「忘れられているのでは」「本当に歓迎されているのか」と不安を感じてしまうこともあります。
このような不安を解消するには、入社前にも定期的にコミュニケーションを取ることが重要です。たとえば、入社予定者向けの勉強会や懇親会、オンラインでの情報共有など、繋がりを感じられる機会を設けることで、心の距離はぐっと縮まります。もし不安に感じていることがあれば、早い段階で把握して対処できるチャンスにもなります。
期待を言葉にして伝える
「あなたの力が必要なんです」「一緒にこのプロジェクトを進めたいと思っています」といった言葉には、何より大きな力があります。求職者にとって、自分が会社に期待されているという実感は、入社意欲を高めるきっかけになります。
言葉にして伝えることで、求職者は「この企業は本気で自分を必要としてくれている」と感じ、安心感やモチベーションが高まります。所属部署の責任者や経営層からメッセージを届けることで、より一層歓迎されている実感が深まるでしょう。もちろん、プレッシャーにならないような配慮やタイミングも大切です。
自社の魅力をしっかりアピールする
求職者が応募している企業は自社だけとは限りません。ライバルとなる他社よりも「この企業で働きたい」と思ってもらうためには、しっかりと自社の魅力を伝える必要があります。
その際、ホームページや求人票では伝えきれない、職場の雰囲気や働いている人の価値観、会社の未来に向けた想いなど“企業の中身”に触れられる話題を交えると効果的です。さらに、面接官の人柄や振る舞いも求職者の判断材料になります。「この人たちと一緒に働きたい」と感じてもらえるよう、面接官の事前トレーニングや情報共有も欠かせません。
イベントで入社意欲を高める工夫
内定後の不安や迷いを払拭するためには、企業との接点を増やし、「この会社で働くイメージ」が湧く環境を整えることがとても重要です。情報提供だけではなく、実際に人や職場に触れる機会を設けることで、求職者の心はぐっと前向きになります。
ここでは、企業が内定者との関係性を強化し、入社への意欲を高めるために活用できるイベント施策についてご紹介します。
職場見学でリアルな環境を体感
面接だけでは見えづらい「職場の空気感」は、実際に足を運んでみないとわからないものです。選考途中で職場見学の機会を提供することで、求職者は働く場所の雰囲気やチームの様子を肌で感じることができ、不安や疑問がぐっと減っていきます。
また、机や設備の配置、休憩スペース、社員の様子などを直接見ることで、「ここで働く自分」のイメージが具体的になるため、内定受諾への後押しにもつながります。
経営層との交流で信頼を築く
ハイクラス人材や経験豊富な求職者にとって、企業のトップが何を考え、どんな未来を描いているかは非常に重要な判断材料となります。経営層との交流の場を設けることで、候補者は企業の課題や展望、組織への思いに直接触れることができ、共感や安心感につながります。
とくに企業ビジョンに納得感が持てるかどうかは、「自分がこの組織の未来に貢献できるか」を判断するうえで欠かせない要素です。トップと直接言葉を交わすことで、志望度が一気に高まることもあります。
同期との懇親会で仲間意識を育む
内定者同士のつながりは、入社に向けた心の支えになります。特に中途採用の場合は、入社後に「孤独にならないか」といった不安を抱きがちなため、同期となるメンバーと事前に顔を合わせておくことは非常に有効です。
懇親会では情報交換ができるだけでなく、「自分と同じ状況の人がいる」と感じることで安心感が生まれます。企業に対しても「仲間づくりの機会を提供してくれる会社」というポジティブな印象を持ってもらえるでしょう。
先輩社員との懇親会でリアルな声を届ける
転職者にとって、実際に中途入社した先輩の体験談は何よりも参考になります。「入社前に不安だったこと」「入社して感じたこと」「職場のリアルな雰囲気」など、同じ立場を経験した人からのアドバイスや声かけは、求職者に安心と具体的な未来像を与えてくれます。
企業側がこうした場を積極的に提供することで、入社後のギャップを減らし、内定者との信頼関係を築くことができます。
まとめ
内定辞退は完全にゼロにすることは難しいですが、企業の姿勢や対応によって「減らすこと」は可能です。求職者の不安や疑問に寄り添い、安心して「この会社で働きたい」と思える環境を提供することが、採用力の向上につながります。
この記事が、求職者の皆さんには企業選びの参考に、法人企業の皆さんには採用活動の見直しのヒントになることを願っています。