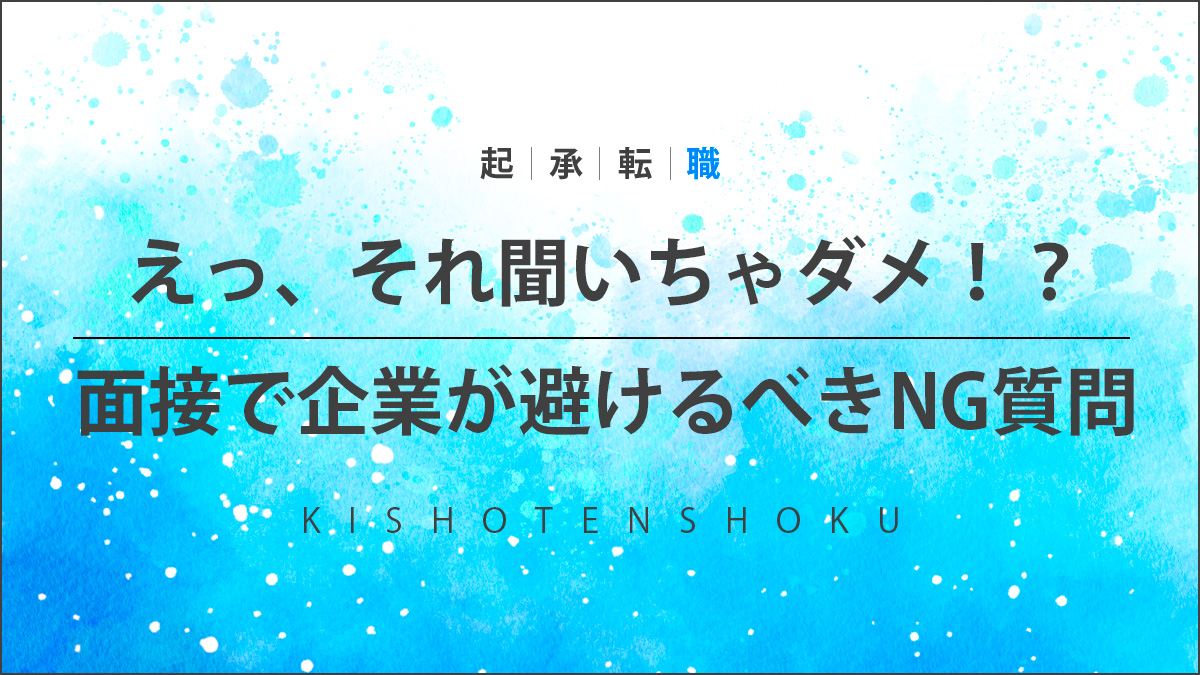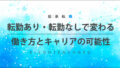採用面接と聞くと「応募者の能力を見抜く場」だと考えてしまいがちですが、それだけではありません。今の時代、面接は企業と求職者が互いを知り、信頼関係を築く貴重なコミュニケーションの場でもあるんです。
だからこそ、「少し気になったから」「場を和ませたかったから」といった曖昧な理由で、応募者のプライバシーに踏み込んでしまうのは絶対にNG。本人の適性・スキルにまったく関係のない質問は、企業の評価を下げる原因にもなりかねません。
この記事では、ついやってしまいがちなNG逆質問の具体例とそれによって起こるリスク、そして面接官としてどんな準備をすればいいのかまで、しっかり解説します!
法律も企業の印象も守るために――個人情報の扱いは慎重に
まず知っておきたいのが「職業安定法」の存在。求職者の個人情報を扱う際には、業務に本当に必要な範囲に限定して収集・利用しないといけません。
つまり「業務に関係ない情報=聞いてはいけない内容」なんです。面接の冒頭での雑談でも、「本籍はどちらですか?」などと聞いてしまうと法律違反になる可能性があります。
知らなかったでは済まされない事例もあるため、企業として面接の準備を整えることが求められています。
面接官が注意すべきNG逆質問とは?
面接官として、「応募者のことをもっと深く知りたい」「コミュニケーションのきっかけを作りたい」と思う気持ちは自然なことです。でも、採用面接の場では、その“好奇心”や“会話の糸口”が意図せず応募者のプライバシーに踏み込む内容になることもあります。しかも、その一言が求職者の信頼を失ったり、法令違反に該当したりする可能性すらあるんです。
ここでは、無意識のうちに面接官が口にしてしまいがちなNG逆質問の例を紹介します。「えっ、そんなこともダメなの?」と思うような話題が意外と多いので、ぜひ確認しておいてください。
本籍・出生地について聞くのは差別の温床に
「どこ出身ですか?」という一言にも、差別に繋がるリスクが潜んでいます。過去には地域による偏見や就職差別の問題が社会問題化してきた歴史があり、応募者本人の意図とは関係なく、出身地や国籍を理由に採否を判断するような事態につながる恐れもあります。
意図がなかったとしても、応募者に不快感や警戒心を抱かせる可能性が高く、結果的に企業への印象まで悪くなることも。たとえ雑談のつもりでも、こうした質問は避けるべきです。
家族構成や収入・職業などの質問は人権侵害になりかねない
「ご両親の職業は?」「大学の学費はどうされたんですか?」といった質問もNGです。応募者の能力やスキルを評価するのに家族構成や経済状況は関係ありません。
特に父子家庭や母子家庭など、家庭の事情は本人に責任のない要素ですし、それを踏まえて評価が変わるような採用は、公平性を著しく欠いてしまいます。こうした個人情報は、面接官が触れるべき内容ではありません。
思想・宗教・尊敬する人など、価値観に関わることもNG
「尊敬する人物は?」「どんな新聞を読んでいますか?」などの質問も、応募者の思想的な背景に深く関わる情報です。一見すると雑談のようですが、憲法で保障された「思想の自由」「信教の自由」に踏み込んでしまう行為にあたるため、非常にデリケートな話題です。
採用選考では、こうした価値観による評価をしてはいけません。たとえ話題のマンガやエッセイだったとしても、思想と結びつけられる可能性があるならば、面接では避けるべきです。
居住地域や住居状況の確認も地雷
「今のお住まいは〇〇市ですか?」「マンションは何LDKですか?」など、住まいに関する話題もNG質問に該当します。間取りや地域の特徴を聞くことは、応募者の生活レベルや資産状況を推測する意図と受け取られてしまうリスクがあります。
応募者にとっては「この会社は住環境まで見て判断するのか」といった疑念を持つ原因になりかねないため、業務に関係のない話題は極力避けましょう。
性別やプライベートに関する話題は慎重に
「結婚後も働きますか?」「交際相手はいますか?」といった質問は、雑談のつもりでもNGです。性別やライフスタイルに踏み込む内容は、男女雇用機会均等法にも抵触する可能性があり、非常にセンシティブな分野です。
さらに、LGBTQ当事者の方に対して質問する場合は、相手の心身の安全を守ることが前提になります。トイレや更衣室などの対応を確認したい場合も、採用後に配慮をもって話し合うようにしましょう。
身体・健康・見た目に関わる質問は原則NG
「身長は?体重は?」「持病はありますか?」といった質問も、原則としてNGです。一部の職種(例:モデルや警備職、自衛官など)では身体的要件が求められる場合がありますが、それ以外の職種では採用選考時にこうした質問をするべきではありません。
特に「制服のサイズを知るためにスリーサイズを教えてください」といった質問は、プライバシーの侵害に直結しますので、絶対に避けるようにしましょう。
NG質問が企業にもたらす“見えない損失”
「ちょっと聞いてみただけ」「悪気はなかった」――そうした言葉では済まされないのが、採用面接におけるNG質問の怖さです。応募者の人権やプライバシーに配慮できない面接は、求職者との信頼関係を崩すだけでなく、企業側にもさまざまな形でダメージを与える可能性があります。
ここでは、具体的にどんなリスクが企業に降りかかるのかを3つの側面から見ていきましょう。実は目に見えづらい損失ほど、企業の将来にじわじわ響いてくるのです。
面接の効果が激減する
面接官の質問によって応募者が動揺したり、心を閉ざしてしまったりすると、本来のスキルや人物像が引き出せなくなってしまいます。「面接=ジャッジの場」ではなく、「相互理解を深める場」であることを忘れてしまうと、せっかくの採用機会を逃す結果にもなりかねません。
さらに、面接で居心地の悪さを感じた応募者が、自分の本音を話せずに終わってしまえば、企業としてはその人物の真価を見抜くことができなくなります。つまり、NG質問は企業にとっても「もったいない選考」にしてしまう要因となるのです。
SNSでの炎上で企業ブランドが崩壊
「面接で不快な質問をされた」といった体験談は、今や個人のスマートフォンから一瞬で世間へ拡散します。X(旧Twitter)やInstagram、TikTokなどを通じて拡散された不適切な面接エピソードは、企業イメージに直結する重大なリスクです。
たとえ悪意がなくても、NG質問は受け取る側の心に強い違和感を残すもの。SNSでの炎上は、採用活動だけに留まらず、消費者やビジネスパートナーにも影響を与える可能性があるため、企業ブランディングの観点からも十分に注意すべき問題です。
法令違反による罰則や通達のリスク
面接時に求職者のプライバシーを侵害するような質問をしてしまうと、内容によっては「法令違反」と認定されることもあります。職業安定法や男女雇用機会均等法など、関係する法律の趣旨を正しく理解しないまま面接を進めると、企業は行政指導や罰則を受けるリスクにさらされます。
それだけではなく、法令違反が公になれば、企業の採用活動自体に制限がかかったり、求人を出しても求職者が応募しづらくなったりするケースも出てきます。信頼される企業であるためにも、面接の場では法令遵守の姿勢を明確に示すことが不可欠です。
タブー質問を避けるために、面接官が準備しておきたい4つのこと
NG質問を防ぐためには、面接官の“意識改革”と“事前準備”が不可欠です。ただ単にタブーを避けようとするだけでは不十分で、企業全体で「正しい採用選考」をつくり上げる仕組みが求められます。
面接の質を底上げし、応募者にとって安心感のある選考体験を提供するためにも、以下の4つの取り組みをチェックしてみましょう。
マニュアル作成でルールを徹底
面接の進め方やしてはいけない質問の具体例をマニュアルとしてまとめておくことで、面接官全員が同じ基準で選考を行えるようになります。個人の感覚に頼ると、質問内容にばらつきが出たり、知らないうちにNG質問をしてしまったりするリスクが高まります。
マニュアルの内容は一度作って終わりではなく、定期的に見直すことも重要です。法改正や社会の価値観の変化に合わせてアップデートすることで、常に「今の面接に適した内容」に整えていくことができます。
模擬面接で質問力をアップ
「何を聞いていいのか自信がない」「応募者との距離感が掴めない」――そんな悩みを抱えている面接官も少なくありません。だからこそ、事前に模擬面接を繰り返すことで、本番での質問の質を高めることができます。
模擬面接は単なる練習ではなく、想定外の受け答えへの対応力を磨く場でもあります。想定質問をリスト化した「面接管理シート」を活用しながら、実際の応募者像に近いシナリオで繰り返し練習すると、面接官の自信にもつながります。
面接後の振り返りタイムがカギ
面接はやりっぱなしではもったいない。終了後には、面接官同士で振り返りを行う時間をしっかり確保しましょう。「あの質問は誤解を招いたかもしれない」「もっと良い聞き方があったかも」といった気づきを共有することで、次回以降の改善がスムーズになります。
また、振り返りでは“よかった点”にも目を向けることが大切です。応募者がリラックスできた質問、自然に本音を引き出せた対話などを洗い出し、マニュアルに盛り込むことで、良い面接スタイルがチーム全体に広がります。
応募者へのフィードバックヒアリング
面接の質を高めるには、面接官の視点だけでは足りません。応募者から直接「答えづらかった質問」や「印象に残ったやり取り」について聞くことで、より客観的な評価が可能になります。
このときは、面接結果とは関係ないことをしっかり説明し、安心して率直な意見を述べてもらうことが大事です。こうしたヒアリングを通じて、企業としての「面接力」が自然と底上げされ、採用CX(候補者体験)の質も高まります。
まとめ
採用面接は、単なる選考の場ではなく、企業が応募者に“どんな姿勢で人と向き合っているか”を示す重要な機会でもあります。応募者は面接を通じて、「この会社は自分を尊重してくれる場所なのか」「ここで長く働きたいと思えるか」を敏感に見極めています。
そのため、面接官の一つひとつの質問が、企業そのものの人権意識や信頼性、そして職場の文化として受け取られます。NG質問を避けることは、単なるマナーではなく、企業のブランディング、法令遵守、そして採用成功に直結する“戦略的な意識”と言っても過言ではありません。
応募者が安心して本音を話せる空気づくりは、優秀な人材の見極めにつながるだけでなく、「この会社で働きたい」というモチベーションにも直結します。面接そのものが好印象で終われば、採用後の定着率やパフォーマンスにも好影響を及ぼすはずです。
これから面接を担当する方は、ぜひこの記事の内容を参考に、「聞いていいこと」「聞いてはいけないこと」の線引きを明確にし、応募者にとっても企業にとっても実りのある面接を目指してください。正しい質問をする力は、信頼される企業文化の礎になります。